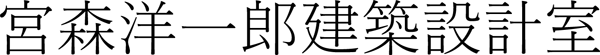ドッグビル
ドッグビルという映画を観た、物語は聞取りの上で展開される。
間どりとは、体育館の床に実寸で描かれた建築、街の「図面」である。
ドア、窓、壁、室名等、正しく図法に従って描かれた図面の上で役者は演ずる。
ドアの上では透明なドアを開き、透明な壁の向こうでは、SEXが行われたりする。
映像がもつべきはずのリアリティが払拭された状態でリアリティのある熱演が展開される。
そのギャップにイライラしながら、普通の映像に戻して欲しい気持ちをずっと抱きながら、そのギャップは埋められないまま、The End を迎える。図面は約束事である。こう書けば、ああなっているということである。
更に言えば建築は約束事である。室名を明記すれば、そのような生活が行われるという約束事の世界である。実際の生活と約束事が作り出した空間とのギャップにイライラするというのが私達の生活かもしれない。
ドッグビルでは、映画が約束事であるという事実を露呈することでストーリー性は、明瞭になっていた。
では建築が約束事にすぎないということをはっきりと認識したときに何が残るのか、建築の約束事、記号性をはぎとった時に残るもの、物質であり、光であり、影であり、風である。
映画における背景とストーリーのように、建築と生活はニワトリとタマゴで分かちがたいが、一度、建築という約束事から、脱出しなければ、建築の真実に近づけないというような気がしてならない。
エレニの旅
エレニの旅という映画をみた。
エレニという女性の半生記であり、悲しい悲しいストーリーである。
美しい映像と音楽で物語は展開され、映画はやはり音と映像の芸術だと実感させられた。
すごいなと思ったのは、彼女の物語でありながら、語られているのは家族であり、社会であり、国家であり、戦争であり、生、人間なのだなということが、見終わって何日かして、しみじみと、感じられることである。
スケール感というのはこういうことを言うのかと思った。
ひるがえって、建築である。
数年前、コルビジェ追想の旅というのに参加した。いくつかの作品を見ているうちに、コルビジェの人物像みたいなものが頭に描けた。
俺についてくれば大丈夫だ。俺が皆を幸せにしてやる!頑固で強情なオヤジ像。
作品にも、少し押しつけがましいがどこか暖かいオヤジの手のようなものが感じられた。
エレニが遭遇する様々な出来事、その背景に感じられる作者のスケール。
建築も、最後のところは、その辺が本質として残るところかもしれない。
映画が、映像、音とストーリーで、人間を語るものであるなら、建築では、何で何を語るのか。
少なくとも、表現のための表現というショートサーキットの世界には入り込まないようにといういましめだけは強く抱くことができた映画であった。
レイ
レイという映画を観た。
冒頭、眼の見えなくなった子供のレイが、部屋の片隅で動いた虫をつかまえるのを見て、母親が涙する というシーンがあった。
眼が見えないというハンディを克服してこれからを生きていく可能性を感じての涙である。
しばらくあとに、帝釈峡の国民休暇村のキャビンに家族で行った。
あいにくの雨でデッキで、ぼんやりと降る雨を眺めていた。眼が見えないとはどんなことなのかと思って目をつぶり、耳をすました。
雨を見ていた時はザーザーというだけの雨の音だったのが、耳を澄ますと、屋根を打つ雨の音、軒先から落ちてデッキを打つ音、落葉に降る音、更に落葉の下を流れる水の音まで聞き分けられるではないか。
まさに色んな楽器が合奏してザーザーという音を奏でているかのようであった。
随分昔のことであるが、大阪南港の安藤忠雄設計のライカを見学に行ったことがある。
打放しコンクリートに囲まれた大空間のロビーでは勅使河原蒼風の作品が展示されていた。
ナマコ状の大きなアルキャストの器にまだ穂のついていない稲が垂直に立ちならんでいる。そんな作品だったように思う。
作品は静寂をテーマにしたものだったと思うが、ホールは空調の乾いた吹き出し音が耳につきザーザーと落ちつかない空間であった。
写真にすれば感ずることができたかもしれない静寂は、現実には存在しなかった。
以前、感動した建築体験を教えて下さいという雑誌社からのインタビューがあり、京都の町家での体験を語ったことがある。
真夏の蒸し暑い陽ざしの中を歩き町家についた。
格子戸を引いて中に入ると、薄暗く、涼しい空気の中に、ほうり出された感じであった。スーッと、汗がひき、奥行きのある空間の中にポツンといる自分が感じられた。
急に暗くなり、梁を組んだ天井の高さも、奥深く続く通り庭が見えた訳ではないのだが、その空気の差は、空間を感じさせた。
眼の見えない人も建築に感動できるのだろうか。もしできるとしたら、どのようなつくり方で出来上がった建築なのだろうか。
建築は空間アートだ、体験アートだと言いながら私達の建築体験は実際には殆んどが写真体験である。
眼の見えない人には全く意味のない世界を出発点としてそこに帰結している面がある。
そうではなくて、風や光、温度や湿度、音の反響や吸音等、眼に見えないこと、空気の質の様なものをデザインの対象とできないものだろうか。
見えないものをデザインするそのデザイン手法を探そうといている者にとって、映画「レイ」は、一つの方向を与えてくれるものであった。
眼が見えないという前提に立って建築を考えるという方法である。
これは計画の理論や手法ではないが見えないものをデザインするスタンス、姿勢のようなものにはなり得るように思われる。とたんに、色は意味を失い、形もデザインの対象とはなってこない。
それに替わってもっと重要なことが浮かび上がり、新たな建築の可能性が生まれてくるのではないか。
そんなことを期待して、眼の見えないことを前提とした建築づくりを続けてみたいと思っている。